
とびラボ初企画!患者の声から学ぶ。差別や無理解を乗り越え “病と向き合い、生きること” を知りたい
「とびだす“R”ラボ」の初企画
職員が今の担当分野にとらわれず、自分自身の関心で新しい出会いや学びを求めてチャレンジすることを応援する「とびだす“R”ラボ(とびラボ)」プロジェクト。
今回は、とびラボとして初の企画となる「患者の声から学ぶ」を皆さまにご紹介します。
病気と差別の問題を、当事者の声を聞いて考えることを目的とした勉強会を開催。この勉強会に込めた企画委員の思いや当日の様子、そこでの職員の気づきを、広報誌「厚生労働」に掲載しました。そして、その記事についてはnoteでも発信していきます。
*「とびラボ」の詳細は、前回の記事をご覧ください。
*広報誌「厚生労働」では、医療、介護、福祉、年金、子ども・子育て支援、労働環境の整備、雇用対策など、厚労省が関わるさまざまな制度や政策について毎月分かりやすく発信しています。職員が登場する一部の記事も読むことができるので、ぜひご覧ください。
*なお、この広報誌は、外部の発行事業者が企画・編集等を行い、厚労省は編集協力という形で関わっています。
企画提案者の思い
「コロナ差別」をきっかけに
病気と差別の問題を当事者の声を聴いて考える

新型コロナウイルスの流行により、私たちは今まで以上に病気というものを身近に感じる機会が増えたのではないかと思います。「コロナ差別」といわれるような、病気をきっかけとした偏見差別についても社会問題となりました。
感染が抑えられている地域で陽性者が出たときの、当事者と家族に対する批判や冷遇、海外でのアジア人への暴言・暴力などのニュースを目にしたとき思わず脳裏をよぎったのは、偏見差別のため長年肉親とも会えずふるさとに帰れないハンセン病回復者のお話でした。この歴史を決して繰り返してはならない、そう思ったとき、とびラボの企画で病気と差別の問題をテーマにしたいと思いました。
明確な偏見差別でなくても、病気や当事者への無理解などが社会における生きづらさにつながっていることはあるのではないか。誰もが当事者になり得る時代、病気や障害をとりまく課題を身近なものとしてとらえ、誰もが生きやすい社会にしていくために私たちができることを考えてみたいと思い企画しました。
子どもも持てず司法も介入できない隔離

ハンセン病とは、らい菌による感染症で、発症自体はまれであるものの末梢神経の麻痺により瞼や唇が下がる、手足の変形、手指の欠損など外形の変化を伴うことも差別の原因となってきました。また、家族内感染があることから遺伝病であるとの誤解もありました。

日本では1907年に〝癩予防ニ関スル件〟のもと隔離政策が開始されました。療養所に入ると持ち物や所持金は取り上げられ、逃走防止のため、うどん縞の着物と園内だけで使える園内通用券を渡されました。
戦前の療養所は極端に医師や看護師、職員の数が切り詰められており、看護や介護、洗濯、土木作業などあらゆる場面で、患者である入所者を強制的に働かせないと療養所の運営が成り立たない仕組みになっていました。
療養所では、子どもを持つことは許されず断種・中絶を強要されました。海外にはこんな例はありません。このため、日本の入所者は病気が治った後も自分の子どもや孫と過ごすことができず、社会に戻るための支援・基盤がないのです。
さらに、戦前の療養所内は司法も介入せず、園長の一存で所内に設けられた監禁室で懲罰が行われました。死後は療養所内の火葬場で火葬され、家族に引き取られないまま、今も療養所内の納骨堂に何千柱という遺骨が眠っています。
戦後、特効薬が開発されハンセン病は治る病気になりましたが、なお隔離政策は続けられたため、入所者の方々が立ち上がり、患者運動により待遇改善やらい予防法廃止を勝ち取っていきました。
らい予防法が廃止されても、回復者の方々の社会復帰は難しく、現在入所者の方の平均年齢は87歳となっています。患者の人権本位に考える視点を失い、社会防衛を最優先にしたハンセン病政策の歴史が今の社会に示唆するものは大きいと思います。

私の心に重く響いた言葉「元通りにはならない」
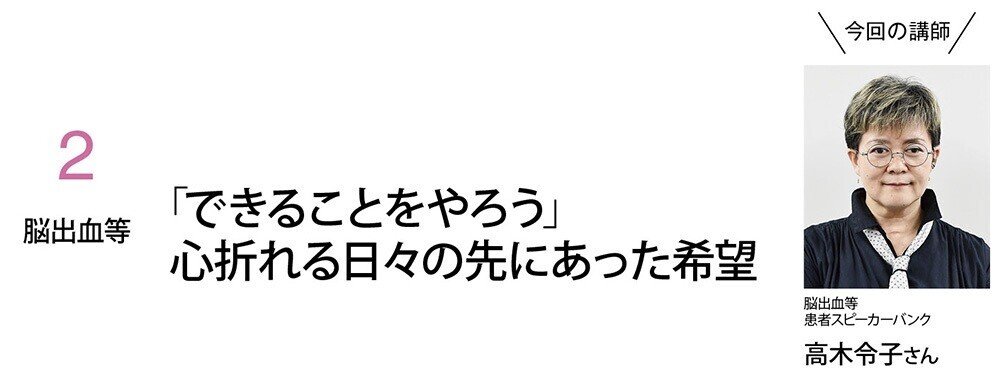
私は、7年前に脳卒中の一種である高血圧性視床出血を発症し、一人暮らしの自宅で倒れました。病院で治療を開始するまで10時間以上経過していたため、初期治療が致命的に遅れてしまい、一時は意識不明の重体に。意識が戻ったとき、右半身は全く動かず感覚もありませんでした。
医師からは、「リハビリ次第では、失われた脳の機能や回路を新しく創り出せる」と言われましたが、同時に告げられた「元通りにはならない」という言葉ばかりが心に重く響いていました。
退院時には杖歩行ができるまでに何とか回復したものの、右半身の感覚はほとんどなく、手先がわずかに動くだけ。麻痺は視覚にも及び、両目から入ってくる情報が一つの像として結びつかない「複視」の症状もありました。
ケアマネジャーや友人を支えに受け入れた「今の自分」
退院後は、現実の厳しさに直面し、何かやろうとするたびに心が折れ、プライドは傷つき、とてもみじめでした。私の気持ちはきっと誰にもわからない、生きていても仕方がない、と死ぬことばかり考えていました。
そんな私の気持ちをケアマネジャーは受け止めてくれ、回復や挑戦を一緒に喜んでくれました。
昔からの友人は、私が障害者になったことなどまるでなかったかのように、以前と変わらず接してくれました。私が「死にたい」と口走ったときは、「ほっといても人間いつか死ぬのだから、生きてるうちは生きとったらいい」と返され、「今の自分を受け入れていこう、できることをできるだけ」と覚悟を決めることができました。
心の「バリアフリー」
こうして私は、「できない理由」ではなく「できる方法」を考える生き方を選びました。
「リハビリを頑張っている障害者」ではなく、生き生きしている一個人でいたい、「障害のある人もない人も互いに支え合い、生き生きと明るく豊かに暮らしてゆける社会づくり」=「ノーマライゼーション」。そのために必要なものは、互いの立場を「知ろう」「理解しよう」とする「心のバリアフリー」ではないでしょうか。

HIV感染の告知に職場は……

自分のセクシャリティーに関して幼少時から自覚がありましたが、当時は学校での性教育はほぼなく、HIVについて教わることもありませんでした。
大学生のときゲイサークルに参加し、翌年友人からHIV陽性のカミングアウトを受けました。そして、2002年に自分もHIVの感染を告知されました。当時は、有効な薬もあり、感染してもすぐに死に至る病気ではないとわかっていましたが、命の期限を突きつけられた気がしました。
私は職場の直属の上司に陽性となったことを報告しました。その上司は好意的な反応でしたが、数日後に部長から呼び出され、退職を促されました。その後、退職の件は撤回されたものの異動を命じられたのです。
異動先では簡単なルーティンの仕事だけで、物理的にも窓際のパーテーションで区切られた空間に私だけ追いやられました。噂が飛び交いましたが、病気のことを口外するなと厳命されていて、理由を言いたくても言えませんでした。精神的に追い詰められ、4年後に自分から退職しました。
いまだに1980年代の古い情報に縛られたまま
近年、HIVの研究・調査は積極的に進められており、適切に治療を行えば、ウイルスは血中、体液中から検出されなくなり、検出限界未満の状態では他者に感染させないことがわかっています。しかし、社会はエイズパニックと言われた1980年代の古い情報に縛られたままのため、いまだに差別と偏見の目が向けられています。
たとえば、私が経験したような職場での差別。同様の例はいくつもあります。陽性者が一番心配しているのは、勤務先に知られることなのです。
仕事以外にも、診療拒否に遭ったり、介護施設への入居が断られるケースもあります。特に地方では顕著です。
陽性者は周囲に言えないことを抱えていることで生きづらさを感じながら生活していますが、誰にでも秘密はあるものです。言いづらいことをあまり気にせずに生きられる社会は、みんな生きやすい。どうしたら悩みを解消しながら生きられるのか。共に考えながら、より良い社会を築いていくために活動を続けていきたいと思っています。

つらかった入院と薬の副作用

私が統合失調症を発症したのは大学3年生のときで、4度の精神科入院を経験しました。統合失調症の症状は主に幻覚と妄想です。20歳前後に発症することが多く、100人に約一人の発症率と言われています。現在は薬物療法などが進歩しているため、治療を受けながら生活していくことができます。
きっかけは不眠からでした。眠れない状態が1か月ほど続き、自分が太陽を動かしている、神になったなどの妄想がありました。家族との会話は成立しないし、自分が混乱状態にあるので、わけもわからず家を飛び出し警察に保護され即入院。これは措置入院です。
1回目の入院はつらいことしか覚えていません。薬の副作用により喜怒哀楽を失いました。好きな音楽を聴いても映画を観ても心が動かされず、何をやっても楽しくありません。2か月で退院しましたが、退院後のほうがもっとつらかった。喜怒哀楽のない状態で繁華街などに外出すると、自分一人が取り残されているような気持ちになり引きこもるようになりました。
精神疾患の薬を飲んでいることに負い目があり、自分がほかの人より劣った存在だと感じていました。薬をゼロにして社会復帰したかったので、自分なりに勉強して断薬を実行。しかし、体調がよかったのは2週間だけ。再び喜怒哀楽を失い、音が声に化けるという妄想も経験し再び入院。このときは医療保護入院でした。
精神疾患の薬を飲んでいる負い目を乗り越えて
4度目の入院は、34歳のとき。医師と相談しながらの減薬でしたが、さすがに私は、服薬しながらできることをやればいい、仕事をしようと思いました。そして精神障害者対象の作業所(正式名称は就労継続支援B型)に入所し、約2年後に職員になりました。また、仲間とピアスタッフ協会を設立したり、精神科病院に入院している方たちの権利擁護のための活動を始めたり、最近は充実していてやりがいのある活動をしています。
現在、私は薬を飲んでいる自分を劣っているとも思っていません。統合失調症を抱えながら生きていくことはそう悪くないことを、身をもって伝えていきたいと思います。

【グループワーク報告】
私たちが思うこと・できること
全4回の勉強会を終え、講師と職員が双方向で話す場を設けました。当日のグループワークの様子をお伝えします。
気づかないうちに差別的な言動をとっていないか
全4回の勉強会を終え、参加した厚生労働省の職員たちと各回の講師たちとの対話の機会としてグループワークを行いました。講師が直接参加するグループと、オンラインで参加するグループとに分かれて、「偏見・差別を解消していくために私たちができること」について議論しました。


「気づかないうちに差別的なことを言っていないか、行動をしていないか心配になる」と話す職員に、「たとえば、週5日フルタイムで働いている、正社員である、公務員である、ということは皆さんにとって普通であっても、それができない人からするとそれは『とてもすごいこと』です。そんなつもりはなくても、無自覚に強い立場にいる、ということを自覚するだけでも変わります」と、講師の高木令子さん(脳出血等・患者スピーカーバンク)が話しました。
また、厚労省でコロナ差別・偏見防止の啓発に取り組む職員は「行政として正しい言葉・表現を使っていきたい。たとえば、『撲滅』という言葉を使用したときに、その言葉がどこに係るのかが曖昧な場合は、誤解を招いてしまったり、誰かを傷つけてしまうこともあるかもしれない」と指摘しました。
当事者の声を聴く重要性
当事者のことを知る機会や情報発信が足りないのではないか、との議論では、講師の堀合研二郎さん(統合失調症・森の庭)は、「テレビや社会の目につくところで統合失調症の人が出てくることはほとんどなく、まるでこの世に存在しないかのように扱われているような気になることも」と指摘しました。
職員からは「マスメディアによる日常的な発信も重要」との意見や「相互理解の重要性を感じるとともに、よかれと思っての気遣いが重荷になってしまうこともあることを知りました」との気づきも語られました。
グループワークの最後に、各グループでの議論を発表し合いました。共通して見出されたのは「当事者の声を聴く機会の重要性」。「お互い直接話してみること」がシンプルだけど大切なこと、今後もこのような交流の機会を増やしていきたいと締めくくりました。
企画委員から

出典:広報誌『厚生労働』2022年2月号
発行・発売:(株)日本医療企画
編集協力:厚生労働省

